座談会
入社の経緯
まずはイプソスに入社した経緯を教えてください。
K.I(男性、2010年入社):
今でこそ海外調査を担当していますが、実は学生の頃は金融業界志望だったんです。学部は商学部金融学科で、卒業後アメリカに留学してからも金融専攻でした。
帰国後、故郷の地方銀行に入行して、貸し付けから保険までいろいろな仕事に携わりましたが、やはり海外と仕事をしたいという意向があったため、イプソスの門を叩いたというのが入社の経緯です。
K.N(女性、2015年入社):
私は学生時代、経営学を専攻していました。修士課程を終えた後、4年ほど政府機関で働いていました。日本企業の海外展開に携わって、日本の製品を世界に広めていきたいという想いがあったんです。でも、実際に仕事を進める中で、進出先の国に関するデータが整備されていなかったり、そもそも揃っていなかったりというのが障害になっているのではないかと感じるようになりました。
それなら、そのデータを作り、整備していく仕事を行いたいと、グローバルに展開する調査会社であるイプソスに入社しました。
S.T(女性、2013年入社):
前職のインドに特化したコンサルティング会社では、市場進出にあたって必要なBtoB調査をしていました。もともと学生時代にアラビア語を勉強していたこともあって、インドを起点にアラブ諸国をはじめとした、新興国のビジネスにも関わりたいという想いがあったんです。そんな折り、会社が東京拠点を縮小することになり、思い切って転職することにしました。
よりグローバルで、かつ、より消費者に近いビジネスができるイプソスは非常に魅力的だったのが入社の決め手です。
現在の仕事
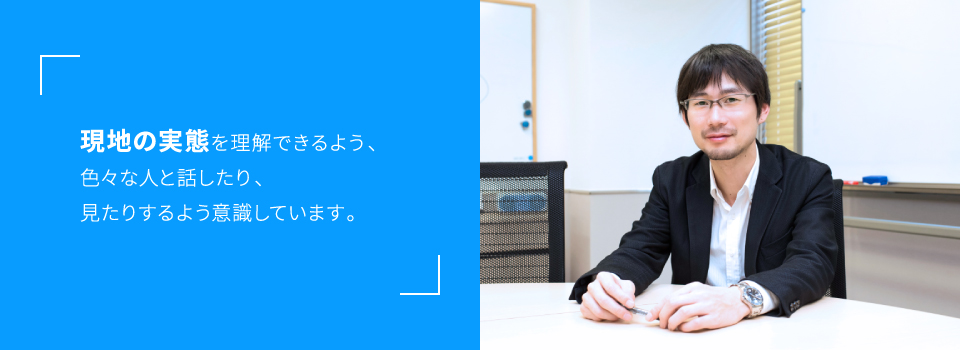
海外調査に携わる皆さんの、現在の仕事について詳しく教えてください。
K.N:
海外調査には、海外企業が日本進出にあたって国内市場を調査するパターンと、日本企業が海外展開するにあたって海外市場を調査するパターンの二つがあります。どちらも、イプソスのグローバル各社と連携して調査を行います。
K.I:
私は食品業界がメインのクライアントです。
最近の仕事で言えば、日本の調味料メーカーが東南アジアで調味料販売を展開するうえで、現地の人々の食生活を知るための食日記調査を行いました。モニターの方に、毎食を記録してもらって、「どのような食事・食材・調味料をどんな頻度でどれくらい使っているのか」を生きた情報として収集する調査です。
K.N:
私も一緒に食品業界のクライアントを担当しています。その食日記調査では、立ち上げ前にクライアントとともに、実際にお宅訪問を行いました。現地の人々がどんなものをどのように食べているのかを見学したり、どんな間取りでどんなキッチンなのかを観察したり、冷蔵庫の中を見せてもらったりと、調査前提となる現地の空気感を把握することができました。
K.I:
肌感覚を持っているのと持っていないのでは大違いなので、出張に行った際には、現地の実態を理解できるよう、色々な人と話したり、見たりするよう意識するようにしています。
K.N:
また、新商品を世に出すにあたっては、その商品を実際に現地の人々が食べてどう評価するかといった試食調査や、商品やブランドのネーミングについて、どんな発音だったら現地になじみやすいのかを聴取したり、その発音が現地では避けなければならないネガティヴなものになっていないか確認したりといったことまで、多岐に亘る調査を行います。
K.I:
試食調査は、ホテルの展示会場で、一週間くらいかけて行います。期間中、しっかりと現地で指導を徹底して、レシピ、特にシーズニングの量といった提供状況を完璧にすることが重要です。というのも、人の舌はちょっとしたことに影響される敏感なものですから、調査のクオリティに直結してしまうのです。
S.T:
主なクライアントは自動車メーカーです。最近の調査では、「どういう技術が評価につながるか」を知る目的で、複数か国で運転の安全意識について調査しました。
国ごとに、対象者が持っている車の特徴によってグループ分けし、それぞれ安全に対する価値観や求められる技術についてインタビューを行いました。だいたい各国6人ずつのグループを12組といったボリュームです。定性調査で得た結果をもとに、さらに各国1,000名ほどのオンラインアンケートで定量的に調査結果を確認するという流れでした。 複数か国のうち、私は東南アジアを担当しました。同じ国でも都市によってマインドが全然違うのでどう切り取るか、どう調査してどう共通項を見いだすかが重要になってきます。日本でも地域によって運転マナーやスタイルはだいぶ異なりますし(笑)。
仕事のやりがい
仕事を通して、どんなとき/どんなことにやりがいを感じますか?
K.N:
私が携わっている食生活の実態調査は、すぐに商品に結びつくものでこそありませんが、その調査結果は、ガイドブックに載っているような紋切り型のものとは違って、私たちが一から収集したリアルな今現在の食生活を体現したデータです。この他にはない情報をうまく活用すれば、「自分たちの仕事が、クライアントに新しい視点を与える」という実感が得られること、それがこの仕事の一番のやりがいです。
S.T:
そうですね。一般的に知られていること・語られていることと、目にされているもので検証されていないものが海外市場などではみられると思いますが、それを数字で裏付けていくことで、新たな視点につなげていければクライアントに意味のある結果につながると思います。
新たな視点につながりそうな調査結果であればあるほど、そのデータやプロセスの信憑性をしっかりと検証する必要があります。
K.I:
二人が言うように、データを活用してもらうことこそ、リサーチャー冥利に尽きます。特に嬉しいなと思うのは、クライアントの現地法人担当者と会うたび、「調査データを使わせてもらって助かっています」というお言葉をいただいたり、「こんなことできませんか?」といったさらなる要望をもらったりと、データを頼りにしていただいているのがひしひしと伝わってくる時。「自分の仕事がクライアントに役立っている」と実感できる時です。
あとは、出張先のクライアントともにスーパーをはじめとした食料品店を回る際、現地の人々がそのクライアントの商品を手に取る姿を目の当たりにする時。クライアントと現地の人々をしっかりと結びつけて、「もっと役に立ちたい」と意を新たにします。
S.T:
お二人が手がける食品にしても、私が担当する自動車にしても、調査してから上市するまではだいぶ時間がかかるものですが、それらが世に出て、生活に浸透していくという達成感が味わえます。
それから、海外調査はグローバルに行ううえで、イプソスのグループ会社の同僚とやりとりしながら進めていきます。ある時、ブラジルのスタッフと定性調査のやりとりをしていたのですが、地球の反対側ですし、「コミュニケーションで齟齬があってはいけない」と意識的に丁寧に仕事を進めていたところ、「あなたとの仕事はとてもやりやすい」って言ってもらえて、とても嬉しかった覚えがあります。こういうふとしたことも、やりがいだと思っています。
K.N:
グローバルネットワークは、イプソスの大きな強みです。たとえばある国の市場を調査する際に、大抵の場合、イプソスの現地採用されたメンバーと協働するので、大変心強いです。この強みを最大限に発揮するためには、スムーズな連携が欠かせません。
各国とのコミュニケーションは、先ほども話にのぼったような気配りが重要です。国籍が違うからというより、単純に遠隔コミュニケーションだからというのが大きいと思います。普段より意識的に丁寧なコミュニケーションを心がけないと、あらゆる面で齟齬が出てしまったり、優先順位や重要度だったりを見失い、混乱を招いてしまうこともあります。
K.I:
そうですね。それぞれ文化や前提条件も違うので、「あうんの呼吸」を期待してはいけないんですよね。
先ほどの食日記で言えば、私としては当然作って食べたものを撮影して添えてもらえるものだと思っていたのに、「料理の種類がわかればいいんだろう」と、ネットから拾ってきても良いと解釈されてしまったなんてことがあります。ちょっとした確認を怠けず、「何のための調査で、食日記では具体的にどんな風に撮影して欲しい」としっかり指示すべきだと学びました。
あとは、単純に時差ですね。特に南米は完全に逆転していますからお互い時間感覚がつかみづらいんです。
S.T:
南米の同僚から、帰り際にチャットで「hi!」と挨拶されて、捕まってしまうのもあるあるですね(笑)。
K.N:
逆に言えば、私たちも世界中の同僚に無理を言ってしまっているシーンもあるんです。そんな中、クライアントの要望に応えるために、ありがたいことに遅くまで対応してくれたり、はては週末作業にまで付き合ってくれたりするなんてこともあって、物理的には離れていても、チームの一体感を覚えます。
仕事を通じての成長と成果
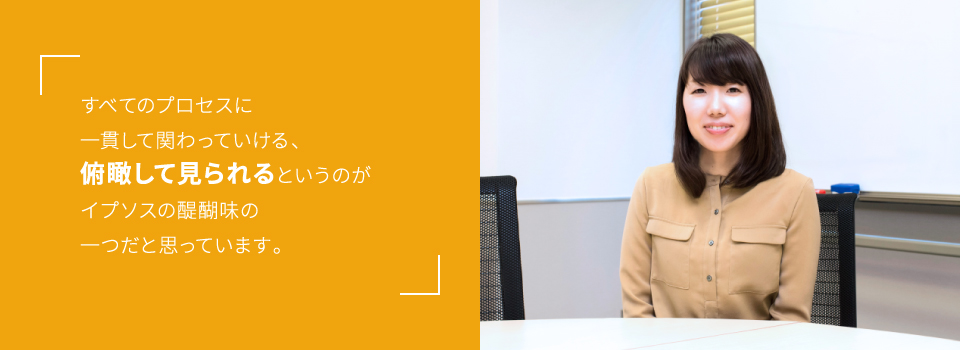
海外調査の仕事を通して、どんな成長と成果を感じますか?
S.T:
やはりリサーチの専門性ですね。開発から上市までのマーケティングプロセスにおいて、そのクライアントが抱える課題に対して、調査を通じて解決していく過程で専門的な知識とノウハウが養われていくと思います。すべてのプロセスに一貫して関わっていける、俯瞰して見られるというのが醍醐味の一つだと思っています。
K.N:
そうですね。個人の専門性が養われていくのに加えて、イプソスが社内に持っているあらゆる調査手法のノウハウ・ツールを組み合わせて、できることや可能性が広がっていくのも楽しいです。
K.I:
実際、長く同じクライアントを担当していると、どんなことをやりたいか、どんな戦略で展開したいかが瞬時に把握できるようになって、たいていの質問に即答できるようになりましたから。
S.T:
あとは、世界中の優秀な同僚たちとともに仕事する中で、「現状維持ではダメだ」と危機感を抱くのも良い刺激になっているかもしれません。
K.I:
刺激になるだけじゃなく、様々な国の人々と仕事をしていると、いろいろな価値観を持った人々と協働するコツみたいなものを体得していける気がします。私自身も、当初はドメスティックな感覚で接してしまい、それで仕事がうまく進まなかった経験を積み重ねるうち、多様性というのものを掴んでいけたのだと思います。
K.N:
協働をしていると、世界で起きていることが「自分ごと」に思えるようになるのも、成長の一つだと考えています。たとえば、ミャンマーの2015年秋の総選挙をはじめとしたアジア各地でのできごとが、自然と自分にとっての身近な話題となります。
マーケティングリサーチのこれから
激動の時代において、マーケティングリサーチはどんな役割を果たしていくと考えていますか?また、そのうえでどんな課題がありますか?
K.I:
かつて食品会社は、主力製品を時間をかけて認知度を少しずつ上げてから新しい製品を投入していくというスタイルを取っていました。しかし、そのスピード感では世界の潮流に対応できなくなっています。
今やどんどん新しい商品を繰り出し、ダメなら迅速に撤退といった即断即決が求められるようになったのです。そんなやり方をたしかにサポートするもの、それが今後のマーケティングリサーチの役割だと考えています。
何かしらよりどころとなる情報がなければ、製品開発もプロモーションもできませんから、リアルタイムのデータ提供でもって、クライアントにスピードという価値を提供する事が重要だと思います。
K.N:
現代はものがあふれている時代。「いいものを作りさえすれば売れる」という時代では必ずしもないかと思います。人々が求めているものは、日々の生活で本当に必要なもの。メーカーはそれに応えるためには、消費者が何を考えているのかしっかり理解したうえで商品を開発することが重要なのではないかと思います。
また、あふれているのはものだけではありません。情報も同じくらい溢れています。だからこそ、ぼんやりとしたステレオタイプではなく、リアリティを持ったディテールを提供していくことが、イプソスの役割の一つであると思っています。
巷に転がっている情報ではなく、企業一社一社に合ったきめ細かい情報。そんな情報の差が、利益の差になっていく、そんな時代なのではと思います。
S.T:
マーケティングリサーチとは、マーケティングの起点となると同時に、その基盤となるものなんです。つまり、マーケティングリサーチなしには地に足のついたマーケティングができないということです。だからこそ、そのリサーチ結果の質のコントロールがよりいっそう大事になっていくはずです。起点で間違えばそもそも進む方向がわかりませんし、基盤がぐらぐらしていると意志決定ができないためです。
K.I:
リサーチャーとしては、専門性を高める一方で、逆に専門家目線ではなく、常に一般消費者目線を忘れてはならないと戒めています。職業病かもしれませんが、ついプライベートでもスーパーの陳列でクライアントの商品を探してしまうんですが、フラットな目で世の中を俯瞰して、目に入るものすべてに敏感でいたいと心がけています。
最後に、そんなマーケティングリサーチの仕事に従事するうえで、職業病だったり、この仕事ならではだったりのエピソードがあれば教えてください。
K.N:
私の場合、仕事でインドのカレーについて調べるうち、スパイスに興味が出て、家でスパイスを使った料理を作るようになる、など良い刺激をもらっている部分もあります。
S.T:
そうですね。出張では現地の生活やより実態に近いところに触れるので、プライベートの海外旅行でも観光地では満足できなくなってしまいました(笑)。もっと生活の息吹が感じられる、ごちゃごちゃしたところが好きです。
K.N:
わかります。私も海外旅行では、カフェなどで現地の人をつかまえて、話かけてしまったりもします(笑)。また、仕事で様々な国とやりとりする中で、新たな言語を学ぶモチベーションも得られます。
K.I:
この調査業界、特に海外調査のことは知らない方が多いと思いますが、本当に国際的な仕事に就きたいと思っている人にとっては、楽しめる仕事だと思います。多くの国の人々と関わるのはもちろん、実際に現地に飛んで、その生活を垣間見ることはなかなか出来ない事ですし楽しいです。
K.N:
リサーチは、マーケティングはもとより、ビジネスをやるうえで、知っておいたほうが良い分野だと思ってます。というのも、企業は大きな資金とリソースを動かすうえで、何らかの根拠が必要となるかと思いますが、そのもととなるデータを扱う仕事ですから。
K.I:
とは言え、入社にあたって「この仕事はいかに黒子に徹することができるかが大切」と宣言されたくらい、地味で地道な仕事ではあります(笑)。
S.T:
たしかに地味ですが(笑)、クライアントの業界や調査課題も多様ですし、様々な手法・ツールが揃っているので、少なくとも飽きることはない、奥深い仕事だと思います。
